くまとりの歴史・文化財
伊勢型紙(いせかたがみ)【町指定文化財】
伊勢型紙とは、三重県鈴鹿市の型紙師によって作られた、染織用の型紙で、室町時代末期には存在していたようです。
熊取と伊勢型紙の関係は、江戸時代の『岸和田当地往来』(当時の教科書)に「熊取紺屋」という記述があり、伊勢型紙を利用した藍染めが行われていたと考えられます。
江戸時代から明治時代の初めまで営んでいた紺屋(染め物屋)から300点近い伊勢型紙をいただきました。これらは庶民の着物などを染める際に使われたと考えられます。
このうち保存状態の良い268点が町指定文化財に指定されています。
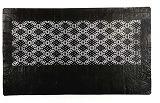
参考文献
『町指定文化財』(平成8年3月 熊取町教育委員会)
大久保E遺跡出土土器(おおくぼいーいせきしゅつどどき)【町指定文化財】
大久保E遺跡は、JR熊取駅の南東部に位置する古墳時代初頭の遺跡です。平成元年から3年に行った発掘調査で数千点におよぶ土器片が出土しました。これらの土器は日常的に使用したものであることから、人々が集団で生活していたことを示すものであり、本町で最も古い資料となります。
残存状態の良い161点(甕(かめ)64点、壷(つぼ)36点、高坏(たかつき)31点、器台(きだい)6点、製塩土器(せいえんんどき)4点、蛸壷形土器(たこつぼがたどき)4点、鉢(はち)12点、甑(こしき)2点、その他2点が、町指定文化財に指定されています。

参考文献
『町指定文化財』(平成11年3月 熊取町教育委員会)
『大久保E遺跡発掘調査概要報告書・1』(平成9年3月 熊取町教育委員会) 1はローマ数字
東円寺跡出土瓦(とうえんじあとしゅつどかわら)【町指定文化財】
現在の熊取町役場、公民館の南側付近には、平安時代末期に建てられた東円寺、または東曜寺と呼ばれる寺院があったといわれ、天正の秀吉の根来攻めのころに焼失したといわれています。
この東円寺があったとされる場所で、平成元年に発掘調査を行ったところ、東円寺創建期、平安末期の蓮華文(れんげもん)軒丸瓦(のきまるかわら)、唐草文(からくさもん)軒平瓦(のきひらかわら)が出土しました。泉南地域の古代から中世期の地方寺院の特徴を表しており、状態の良好な4点は熊取町の指定文化財に指定されています。

参考文献
『町指定文化財』(平成8年3月 熊取町教育委員会発行)
土丸・雨山城(つちまる・あめやまじょう)【国指定史跡】
熊取町南部の雨山(標高312メートル)と泉佐野市の城ノ山にまたがって所在した、南北朝時代から戦国時代の山城です。
紀州と泉州を結ぶ粉河街道を押さえる位置に立地することから、戦略上重要な城で、いくとどなく争奪戦が繰りひろげられました。
発掘調査では、尾根沿いを中心に、曲輪や堀切などの遺構や14~16世紀の土器が発見され、平成25年10月17日に日根荘遺跡の16番目の地点として、国の史跡に指定されました。

現在

昭和9年
参考文献
『土丸・雨山城跡-日根荘遺跡関連調査報告書-』(平成24年3月 泉佐野市教育委員会・熊取町教育委員会)
『史跡 日根荘遺跡保存活用計画書』(平成30年3月 泉佐野市教育委員会・熊取町教育委員会)
『熊取の歴史』(昭和61年11月 熊取町教育委員会)
建武地蔵(石造地蔵菩薩立像)(けんむじぞう(せきぞうじぞうぼさつりゅうぞう))【町指定文化財】
建武4年(1337)に製作された、熊取町内で最も古い、砂岩製の石仏で、もとは正福寺(廃寺)のもといわれています。
文化財としての名称は、石造地蔵菩薩立像と登録されていますが、建武年間に製作されたことから、通称「建武地蔵」と呼ばれています。
光背の銘文には「建武四丁丑十一月日」、「熊取庄阿闍梨■方」と彫られています。
(熊取庄阿闍梨■方の「梨」と「方」の間、■の部分は劣化しており読み取れない部分です)

昭和8年撮影

参考文献
『指定文化財』(平成9年3月 熊取町教育委員会)
この記事に関するお問い合わせ先
生涯学習推進課(文化振興グループ)
電話:072-453-0391
ファックス:072-453-0878
〒590-0415
大阪府泉南郡熊取町五門西1丁目10番1号(すまいるズ 煉瓦館内)













